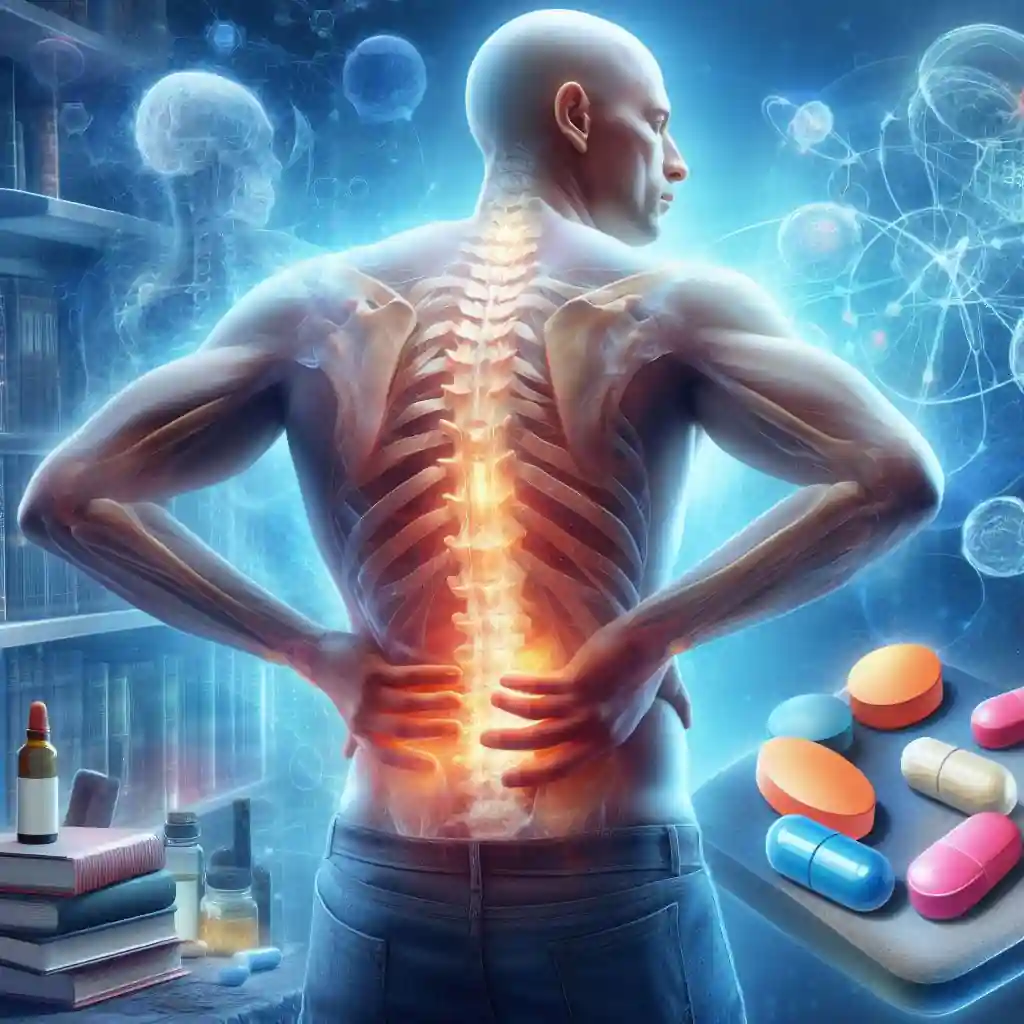ちょっと混乱するかもしれませんが大事なことなので最初に書きます。それは
脊柱管狭窄症は病態を表す言葉であって、脊柱管が狭くなってるという原因(疾患)を表す言葉ではありません。
簡単にいうと「数分歩くと座りたくなるくらい腰が痛い」とか「足に痺れが出てきて」というような状態の時にたまたまレントゲンやMRIを撮影して脊柱管が狭くなっているのが発見されると「脊柱管狭窄症」という診断が付きます。
原因をあらわしている言葉でない
何が言いたいかというと、様々な要因で、数分歩くと座りたくなるという状態を表しているということで、脊柱管が骨化して狭くなっているから歩けなくなっている訳ではないというのが研究者のコンセンサス。
つまり脊柱管が狭くなっている人の中には腰痛や脚の痛みのない人もいます。
私のような一代替医療家が行っても説得力がないでしょうから、世界的に納得のできる質の高いエビデンスを見ていきましょう。
腰痛も下肢痛(かしつう=脚の痛み)も経験したことのない健常者67名を対象にMRIで腰部を調べた結果、1/3の人に変形がみられ20%の人がヘルニア、
椎間板変性・変形性脊椎症・椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症のような構造上の変化はごく一般的な所見であることが判明したことから、手術の選択は慎重であるべき。
脊柱管が狭くなって症状が出ているのなら、なぜ痛みが出ない人がいあるのかということがポイントです。
1999年の研究
椎間板ヘルニアか脊柱管狭窄症によって手術を受けた患者665名を2~4年間追跡した前向き研究によると、
手術実施率の高い地域の治療成績は手術実施率の低い地域よりも劣ることが明らかとなった。手術実施率が高い地域の方が腰痛治療の成績が悪い 。
(Keller RB. et al, J Bone Joint Surg Am,1999)
脊柱管狭窄症も基本的には手術の対象ではない
欧州の腰痛診療ガイドライン
「痺れも含めたすべての慢性的な腰痛に対する外科的な手術は適切な保存療法を行っても2年間変化が無かった場合に、いくつかある方法の選択肢の一つとして行うものです」
「しかし現時点では手術をすることが長期的にみて効果的であるという証拠はどこにも無い。どういった手術が失敗に終わったかを考慮にいれて見当する必要がある。」(2004年時点)
「また腰痛への外科的手術の結果がどのようになるのかについては今までより精度の高い研究をする必要がある」
(European COST for chronic non-specific low back pain2004)
手術した直後は楽になるのですが、1年、2年すると保存療法と変わりありません。それらのエビデンスを見ていきましょう。
これらの事実は、日本の今の医療現場では患者に知らされることは少ないように思われます。
腰痛や痺れ、脊柱管狭窄症の方で本当に手術が必要なのは1%以下です。
(Rosmoff HL and Rosmoff RS Med Clin NorthAm 1999)
術後1~2年は良いかもしれない減圧術 2009年の研究
「脊柱管狭窄症の減圧手術が術後1~2年は非外科的治療より適度に優れている。
椎間板ヘルニアの椎間板切除が術後2~3ヵ月間は保存用法に比べて機能的になるという証拠はあるが、それ以降保存療法と比べて有益であるという証拠はない。
結論として手術は短期的なメリットはある。
(ChouR Baiseden J et al Pain 2009 May )
この短期的なメリットのために手術をうけるのは患者さんの選択になります。ただし手術前にこのことを知らされていることが大切です。
脊柱管狭窄症の症状の実態
冒頭にも買い来ましたが、画像所見と病態は無関係の脊柱管狭窄症であると言っても良い論文です。
高性能の画像診断の普及によって1990年代から脊柱管狭窄症が増加したが、100名の脊柱管狭窄症患者(平均年齢59歳)の臨床症状と画像所見(単純X線撮影・脊髄造影・CT)を比較した結果、臨床所見と画像診断には関連性は見出せなかった。
Spine . 1995 May 15
これは検査機器の向上によって今まで映せなかったものが映るようになったので、これが脚の症状の原因だ!と仮説を立てただけで、蓋を開けてみると違うところに原因があったということです。
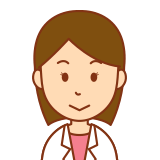 女性ドクター
女性ドクターもう30年も前の論文になるのですね。
それでも手術がしたい方がいる
脊柱管狭窄症に限った話ではないですが、腰痛が原因で手術を行うのは最後は患者さんの選択になるとおもいます。勿論その選択が正しいこともあります。
それも大事ですが、これらの事実があることを知ってからお話し合いの中で決めていくことが医療者の務めであると考えます。しかし世界中宇で狭窄症の手術は増えている…
65歳以上の脊柱管狭窄症による手術件数は1979年~1992年にかけて8倍に増加しており、地域によって5倍の差が生じている。手術成績に関する十分な情報がないまま生死にかかわる治療を選択せざるを得ない状況は好ましくない。
脊柱管狭窄症の術後は感染症が怖い
65歳以上の手術の後は栄養不良と感染が酷い
腰部脊柱管狭窄に対する選択的除圧術と脊椎固定術を受けた患者114名を分析した結果、65歳以上の42%に栄養不良が認められ、術後感染率が85%と高率だったことから、栄養不良は脊椎手術による術後合併症の危険因子である。
栄養不良と術後感染は術後合併症だと、知識としていれておいても損はないでしょう。
2016年の研究 手術の組み合わせの研究
脊柱管狭窄症の減圧術に
①除圧術のみを行った場合
②固定術を追加した場合の2年後と5年後の転帰
を比較する無作為化試験Swedish Spinal Stenosis Study(SSSS)を行い、これらの治療の有効性には差はないこと②固定術を追加すると、出血量が増え、入院期間が長引いて、費用も高額になることを報告http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1513721
除圧術に固定術を追加しても意味はないということです。
すべり症を伴う脊柱管狭窄症への手術
脊柱管狭窄を伴う変性辷り症患者76名を対象に、器具固定群と骨移植固定群の術後成績を2年間追跡したRCTによると器具固定によって骨癒合率の向上は認められるものの、それが必ずしも臨床症状の改善に結びつかないことが判明。
器具固定ですべり症を固定しても意味はないということです。
減圧椎弓切除術 6年後には効果は半減
脊柱管狭窄症と診断された腰下肢痛患者88名を対象に減圧椎弓切除術の成績を6年間追跡した
結果:1年後の改善率は89%だったが6年後には57%に低下し17%は再手術を受けていたことから、これまで報告されていた成績より悪い。
減圧椎弓切除術は6年後には6割の人が再悪化しているということです。手術費用を年換算すると良いかもしれませんね。
脊柱管狭窄症への減圧椎弓切除術に関する論文74件を厳密に検討した結果、優または良と評価できたのは平均64%だったが、論文によっては26%~100%もの開きがあり、研究デザインにも不備が多いためその有効性は証明できない。
減圧椎弓切除術の有効性は証明されていない、という結論です。今でもたまにこの手術をしたという方のお話しを聞きます。有効性は証明されていないようです。
プラシーボ効果を超えない 減圧椎弓切除術
脊柱管狭窄症に対する減圧椎弓切除術に関する74件の論文をレビュー
減圧椎弓切除術によって優または良と評価できた割合は平均64%だったことが判明。やはりプラシーボの平均有効率70%を超えていない。
複雑な固定術を必要とする脊柱管狭窄症がわずか6年で15倍に増加したとは考えられない。脊椎分野のオピニオンリーダーの影響や思い込み、経済的利益などの要因が関与している。正確な情報を与えられれば患者は低侵襲性のリスクの小さい手術を選択するだろう。
こんなことでいいのでしょうか?馬鹿馬鹿しいですね。
腰痛疾患の分野では十分な試験が行なわれることなく新しい技術が普及してしまう。アメリカでは脊柱管狭窄症に対する固定術の実施率が15倍に増加したが、それに伴い重篤な合併症、死亡率、再入院による医療費なども増加している。明らかに過剰診療。
あくまでもアメリカのお話しですから、日本人のお医者さまは器用だから大丈夫かもしれません。
脊柱管狭窄症の治療では、特異的な適応がほとんどない症例や、より簡単な治療で高い効果が得られる明確なエビデンスがある症例に対しても、より複雑な新しい手技(固定術)が行なわれている。エビデンスのないリスクを伴う高価な治療の急増は問題だ。
脊柱管狭窄症で複雑な固定術を受けた患者は、除圧術に比べて命に関わる合併症リスクが3倍(5.6%対2.3%)。術後30日以内に再入院する可能性も高く(13%対7.8%)、手術費用も3倍強にのぼる(80,888$対23,724$)。
手術を終えたばかりの人は「あ~、すごく楽になった」と表現します。貴方の周りの人が、手術後5.6年していくうちに、どんな状態になっているかを観察してみてください。上記のエビデンスが語っている事が理解できるでしょう。
脊柱管狭窄症の保存療法は取り組み方がポイント
ランニングやウォーキングを初めるなど、ライフスタイルを変えていくことがとても重要です。しかしもともと運動していない方なのでそのような容態になっているのですから大変です。
脊柱管狭窄症と診断がでると、手術をいう手っ取り早い方法をチョイスしたくなるお気持ちもよくわかります。けれども上記のような情報を知ってるのか知らないのかは大きな違いです。何とかご自身と向き合って、少しずつ回復させていくことを選択されることをお勧めします。
お身体は正直ですから。
保存療法でどれくらいで回復すると考えるのか?
数カ月から数年と考えてください
脊柱管狭窄症の診断がでていても数回の治療で劇的な改善をする方もいらっしゃいますが、基本的に症状はゆっくりと改善していきます。数ヶ月~年単位で考えたほうがよいです。
保存療法の成績としてのデータとしては、3~8年の追跡調査で改善が15%~45%です
(Amundsen T,et al.Spine 25 1424-1435 (2000)
変化が無かったものとしては28.8%~75%です。データにばらつきがあるのは、個体差が大きいのと、臨床環境も大きく違うからです。
劇的に変化する場合も勿論あります
これらの研究は1980年代後半から行われているものです。ですから保存療法の対象が温熱療法や機械によるけん引が主体の研究結果ですので、もう少し前向きに考えてもらっても良いかとおもわれます。
状態にもよりますが、典型的な脊柱管狭窄症の症状でなければ早期回復もありえます。ヨーロッパガイドラインを始め、効果的な保存療法の数も増えてきているので、現在では上記の数字よりは高い回復率であると考えられます。情報を入手したらアップデートいたします。