貧しかったころの方が健康的だった。バカバカしい話もあったものです。
面白い研究です。大規模な調査で、米国からのの輸入規制が行われていた1990年代前半、キューバ人は健康だったようです。
1990年代初め、キューバは米国の厳しい輸入規制とソビエト連邦の崩壊により厳しい経済危機に苦しんだ。その結果食事からとるカロリーが減り石油が入手できなくなったために政府が100万台以上の自転車を配り、運動量が増えたからだと推察している。

健康を中心に考えた場合、こういう「なんのこっちゃ」的な研究はあるあるです。
経済危機で食糧難にあるほうが疾患リスクが下がる
5年間の経済危機の間に国民一人当たり5.5kg体重が減った。
この期間に心血管系疾患、2型糖尿病、がんの頻度とそれらによる死亡が減った。しかし危機が過ぎ去ると食べる量が増え運動が減り元に戻った。
先進各国 どこも肥満の問題があります。アメリカのコーラは大きいですものね。あれで太らないわけがない。食べる量が減ると、運動量が増える見たいですね。たしかにお腹いっぱいたべると動こうとはおもいませんものね。
カリフォルニアだったかな?ソーダ税をいち早く徴収しはじめたのは。ソーダ飲料の値段が上がれば買う人が減るので、結果的に疾患リスクが少し下がるそうです。
結局むかしから言われていることが大切なことって多いです。腹八分目とはよく言ったものです。最近私も中年太りぎみで久しぶりに会う方からは必ず【すこし太りましたね】なんて言われるものですから、食べる量が増えたのでしょうね。よくよく考えないといけないとこです…
追記:
2020年で各国ソーダ税を導入して、消費量と税と価格の影響を調べた研究だと、結局ソーダ税が発生しない砂糖含有量に下げられた製品が開発、売れ筋になるから水分量トータルの消費量に変化がないのと、課税前に数か月分の駆け込み需要が発生することが分かったそうな…
Gonçalves J, Pereira Dos Santos J. Brown sugar, how come you taste so good? The impact of a soda tax on prices and consumption. Soc Sci Med. 2020 Nov;264:113332. doi: 10.1016/j.socscimed.2020.113332. Epub 2020 Sep 2. PMID: 32992226.
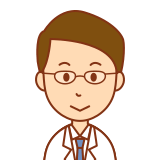 ドクター
ドクターこれも結局なんでやねん!って結果です
21世紀にはいり、病気の形態も随分変化していきています。
今日本は飽食の時代になりますので、いかに無駄に食べないかが健康維持の一つの目標になります。
大手企業は超加工食品を取り扱い、われわれを消費の連鎖に巻き込もうと必死です。
超加工食品はこのページのように砂糖製品、インスタント製品などいかにも美味しくて簡単に手に入るプロダクトです。
欧米ではこれらの食品をタバコやお酒のように危険な嗜好品であると定義する動きが活発です。
皆さんもお気をつけくださませ。









