痛みは一概に悪くない 何かのサインかも
私はカイロプラクティックを通して『痛み』というものが、個々の人間や、その集団、コミュニティーがより良く生きるため、また社会成熟して行く方向性を示しているのではないかと思うようになりました。
超高齢化社会を迎える日本にとって、とても大きな問題かもしれませんが世界に誇れるコミュニティーを作っていけるチャンスであるとも言えます。
痛みはきっと何かのサイン
いつも痛い痛いといっている方。おそらくこれからもずっと痛いでしょう。痛みをコントロールしようとしたら、ライフスタイルを少しずつ変えていく必要があります。
またその痛みは社会的な痛みを回避するために出ている可能性もあります。それらの科学的な研究結果を見ていきましょう。
慢性の痛みは「言葉」によって活性化する
昔から良い言葉を使いましょうと教えられてきましたが、こと痛みに関しては「痛い」という言葉をむやみに使わないほうが良いようです。言葉が痛みを助長することがMRIによって判ってきたからです。

【fMRIを用いた研究】
痛みに関連した言葉とイメージを思い浮かべる時とリラックスした時の脳の活性化部分が違う。注意を逸らせるイメージや言葉だと痛み部分の活性レベルが低下した。
このように脳内の痛みタスクは何に注意をはらっているかで大きく変化する。痛みを考える上で心理学上の負の感情や意識の覚醒状態だけで考える事はできない。
(Richter M, Eck Jet al .,2010)
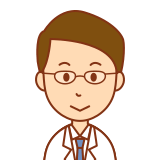 ドクター
ドクターいつも痛い、ここが痛い、ずっと痛いという言葉を使っている人は痛みに注意が向くため、より痛みが強調されますし、脳科学でも証明されてきているということです。
痛みのイメージ、言葉も関連
感情に意識、言葉が関連している痛み
痛み関連コンテンツをイメージまたは言葉にすると背外側前頭前野(DLPFC)と下頭頂皮質という痛みに関連するペインマトリックスが活性化される。これは単に、ネガティブな感情や、意識の覚醒状態の変化によってのみ痛みが変化するのではないことを示している。
(Richter M, Miltner W et al.,2011)



人間ってほんとに不思議な生き物ですね。昔から言われている正しい言葉を使いなさいというのは痛みに関しても言えます。
脳神経は「社会的な痛み」「肉体の痛み」を共有
2012年 心理学のレビュー
社会的な拒絶または損失の経験が、おそらく脳内で正当な理由のために、人間の顔や「痛い経験の一部」として記憶されている。この脳内システム、は社会的分離、(孤立)の有害な影響を防ぐために、痛みの信号を借りて、痛みのシステムを共有しているかもしれない。
社会的な痛み(社会での立場の痛み)は身体の痛みそのもの
このレビューは、物理的な痛みや社会的な痛みの経験が共有神経基質に依存しているという考えを探求してきた研究のをまとめたものです。
社会的な痛みは肉体的な痛みの関連神経領域を活性化することを示す証拠が見つけ出されている。
そして、このような物理的な予想結果のいくつかの身体の痛み、社会的痛みのオーバーラップを探索研究がまとめられている。共有神経基質は社会的に痛い経験の理解のために議論されている。
(Psychosom Med. 2012 Feb-Mar)
痛みの疫学調査では?「痛い奴」との関連


1958年産まれの英国人を45歳の時に見た研究が2008年10月24日に発表
(Ann Rheum Dis 2009)
同世代をグループ分けし追跡比較していくと(出生前向きコホート研究)社会経済的状況と成人期の筋骨格系疾患の関連がある。
これは単純に労働時間が長くなるため肉体的に負担が増えるということとも言えますし、広く言えば格差がそのようにさせているとも言えます。単純には言えないのですが、一般的に言えることの一つです。
アフリカのハッザ族という平等社会では、腰痛のような筋骨格系疼痛は存在しません。人間の幸せを考える上で重要な研究も多く存在します。
オーストラリア 2010年の研究発表
オーストラリアの疫学研究によると腰痛発症率は30代が最も高く、全体の有病率は60~65歳まで増加するがその後徐々に減少する。腰痛発生の危険因子として低学歴・ストレス・不安・抑うつ・仕事への不満、職場の社会的支援が乏しいなどが明らかになった。
(Best Pract Res Clin Rheumatol. 2010 Dec;24)
ここでも社会的地位や、低学歴、仕事への不満などが上げられています。日本はいま格差社会と言われています。おそらく腰痛や首痛といった筋骨格系症状が増えてきているものと思われます。
2008年研究【時に痛みは社会的な痛みとして再発】精神医学の研究
肉体的な痛みが癒えない時は社会的な痛みとして脳の構造に組み込まれることを示唆。
興味深いのは構築された社会的な痛みは、次に同種の社会的苦痛を味わった時に、より強い身体の痛みを憶えるようだということです。
社会的な痛みは肉体的な痛みに便乗して脳の構造に記憶され、進化して社会的な痛みがあった時に身体の痛みより先に認識され、過去にあったような社会的危機に再び合わないように働いていると考えられています。
Chen Z, Williams KD, Fitness J, Newton NC. When hurt will not heal: exploring the capacity to relive social and physical pain. Psychol Sci. 2008 Aug;19(8):789-95. doi: 10.1111/j.1467-9280.2008.02158.x. PMID: 18816286.



これは非常に面白い仮説です。若い人が使う「痛いやつ」というのは言い得て妙なのです。
痛み自体は完全に解明されていないのですが、このような論文からより複雑に社会的なことと関連しあっていることが解明されてきています。
パワーハラスメントと身体の痛み
共同通信社 2012年12月13日(木) 配信によると、厚生労働省は12日、過去3年間に職場でパワーハラスメント(パワハラ)があったと回答した企業が32%に上ったとする調査結果を発表。
従業員に対する調査では、パワハラを受けたことがあると回答した従業員は25・3%で、このうち46・7%は会社への相談などは何もしなかった。
割合は「上司から部下」が77・7%を占め、「正社員から正社員以外」も10・6%あったとあります。さて
カイロプラクティック治療を受けに来られる方は筋骨格系の痛みを主訴としていらっしゃるのですが、こころの痛みが身体の痛みとして出ていることもよくあります。
しつこい首や肩のコリ、これらが極まって痛みや頭痛、吐き気にまで発展していることもあります。通常の肩こりや首痛ですと、数回来院する間に随分楽になってくるものですが、全く変化がなかったり、繰り返してしまう方も少なくないです。この様な場合は、さまざまなストレスがあることが考えられますので、職場のことや家庭のことを伺っていくこともあります。
ネットでのネガティブ活動も避けたほうがいい
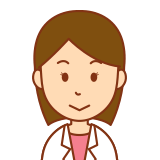
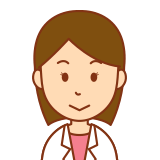
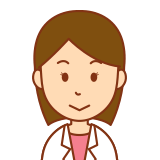
積極的なポジティブな活動が身体の痛み感覚を下げることが分かっているが、ネットでの積極活動も痛みは減るというのです。
ネットを介して、ポジティブな活動をするように介入すると6週間の介入終了時、終了1ヵ月後、3ヵ月後および6ヵ月後で痛みの軽減が統計的有意にあった。
身体の痛みについて自己報告してもらい 多くのポジティブ活動をしたほうが改善がみられたという。ネット社会では匿名での攻撃、誹謗中傷が絶えません。特に日本ではその傾向が強いと言います。
匿名投稿なら問題ないかと言われても、匿名、実名を分ける研究は見たことないですが、すくなくとも「否定的な言葉を使っている」時点で痛みを覚えやすいのではないかと私は思います。
やっぱり人 最後は人
これらのことが医学的な評価としてこのように論文に出されているのは極めて画期的なことだとおもいます。カイロプラクティックにも痛みをとる目的で来院なさる方がいますが、このようにポジティブな方、前向きな方のほうが回復に向かうのも早く、確立も高くなります。
痛みが早くとれますし、費用も少なくてすみます。
臨床現場でおしごとされている方なら、体感的に理解できることですよね。
「病気を診ずして病人を診よ」
という理念は東京慈恵会医科大学創設者の高木兼寛先生によって謳われて130年になりますがこの臨床にあたる心理というのは時代とともに色濃くなっていく気がします。
どんなに医療機器や薬剤が開発されても痛みが消えない、局所麻酔や鎮痛剤、抗うつ剤を処方しても一時しのぎになることが多い。定量以上、ガイドライン上での期間以上の処方、多剤処方と今現在進行して社会問題になっています。
病んでいる人を診るのが我々の仕事なのです。ですから常にそのようなことを促し続けています。カイロプラクターは病気を治しません。
自然治癒力が人を治します。
カイロプラクティックも人を治しません。認知行動療法も人を治すわけではない。
患者さん自身が自分で気づき治ります。
また患者さん自身も自分に向き合い、ポジティブな活動を心がけるようにすることが大切です。われわれカイロプラクターができるのは、いろいろある人生の困難に直面する患者さんの背中を押してあげることだと
私は思います。
人生は面白いものです。その困難自体が幸福への切符であることがあります。
逃げずに、いっしょにそれに向き合って、時間をかけてでも幸福の立ち位置を見つけることをお勧めしています。









